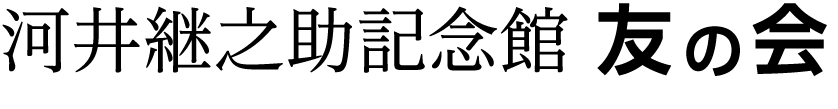稲川通信について
「稲川通信」の著者である稲川明雄前館長は、令和元年12月12日に逝去されました。【41宮路村の騒動】以降の「稲川通信」は、生前にいただいておりました原稿を掲載し、連載を続けます。原稿は、稲川前館長が最終校正をされる前のものですので、現在の考証とは異なっている箇所もあるかと思います。その点をなにとぞご承知のうえ、「稲川通信」をご覧いただければ幸いです。
【稲川通信23】生誕地はどこか
文政年中の長岡城下図をみると、河井代右衛門の屋敷は長町の東南の端にある。その後の城下絵図にも河井継之助の屋敷地の位置は変わっていない。
従来、継之助は同心町から移ってきたという説があった。同心町は町同心の住む同心屋敷があったところである。何らかの事情で、河井家は同心町に逼塞させられていたと考えられてきたが、そういう事実は現在まで見いだせないのである。
この同心町から長町に移ってきたとする説は、河井継之助研究の第一人者安藤英男氏の主張を嚆矢こうしとするものだが、今一度、考証する必要が生じている。
本来、武士と同心の身分は隔世の感があった。たとえ、長岡藩が小藩といえども、騎馬士(大組)に属する河井家が同心屋敷に居候したとは考えにくい。この点について、従来、疑問を持ちつつも、同心町生誕説を採っていたことを訂正する次第である。なお、長町そのものを生誕地とする先学の資料もないことも確かである。
(稲川明雄)

【稲川通信22】 出生時刻に二説あり
継之助の出生時刻には二説ある。つまり、文政十年(一八二七)一月一日の暁七ツ時と同日の正午という二説である。その二説の出どころは、いずれも郷土史家の今泉鐸次郎・省三の父子研究家だ。
父の今泉鐸次郎は畢生の書である『河井継之助傳』を著している。現在、河井継之助研究は、この書によっているといっても過言ではない。
『河井継之助傳』では、出生は暁七ツ時だ。ところが、その令息である今泉省三は、その著作『忘却の残塁』で「今泉木舌氏(父・鐸次郎)によれば、継之助の生まれたのは暁七ツ時・午前四時としているが、一説に午の刻、すなわち正午ごろともいわれている」と述べている。この出典は不明だが、郷土史家独特の取材の中での史実かもしれない。たった八時間の差であるが、この二説を考え合わせると、継之助に対する家族の期待というものが伝わってくる。
(稲川明雄)

【稲川通信21】蒼龍窟の誕生
文政十年(一八二七)一月一日の朝七ツ刻に河井継之助は越後長岡藩(七万四余千石・藩主牧野氏)の城下町に生まれた。干支でいえば、寅の月・寅の日・寅の時刻に誕生したことになる。偶然の一致とはいえ、多少の疑問が残る。
長岡藩士の河井家にとって、継之助の誕生は大いに期待するものがあった。その継之助がみずから蒼龍窟と号するのは、艱難辛苦を体験している雌伏時代の二十八、九歳のころである。誕生のとき、祖父母も両親も継之助が虎のような人物になるよう期待していたのだろう。ところが、継之助が後年、龍にこだわったのは、何か理由があってのことだ。
号を単に蒼龍としただけなら、それは屋敷にあった二本の松樹を模したのかも知れない。また、九代牧野忠精の龍徳院公にあやかって、その若い龍としたのも考えられる。そういえば、忠精公の描く雨龍の図は諧謔性に富むものだ。
ところが正しくは蒼龍窟と称する。それには継之助が己れに課した人生観がこめられていると思われる。
継之助は若いころ、禅を学んだという。『碧巌録』は愛読書だったらしい。龍の喉元にある玉をとれば英雄になれる話がある。あらゆる困難にうちかって、龍の玉を奪い取ろうとする壮大な己れの人生を模していたのではないだろうか。ただ、彼の人生には龍とともにあらわれる瑞雲がたなびかなかったきらいがある。
(稲川明雄)

【稲川通信20】長岡甚句を歌う継之助
大正八年五月発行の「改輯・長岡市案内」(大正社)に
「旧長岡藩の英傑河井継之助は最も甚句に妙を得、美音妙曲の聴えあり。
未だ老職執頭たらざし時、町屋の大通(現今草間病院前・表町三丁目)に於て、
夏の宵、老若男女混合、甚句を謳歌し始めしに、継之助は大刀を背後に押遣り、
義経袴の股裁を取り、扇面を口に当て、音律華朗たる音聲を振り絞り、
音頭の役を勤めし例ありと云ふ」
とある。
その甚句の歌詞も「だいろうだいろう(百姓々々/※原文ママ)つぬ(籾)だせ(可納)だいろう、つぬをださぬと、代かんどん(代官殿)にことわるぞ(可訴)」というものであった。
だいろうはカタツムリのことで、つのは角であったから歌詞の意味からとらえるならば、継之助はどんな気持ちで歌っていたのだろうか。
(稲川明雄)

【稲川通信19】母 貞の述懐
母の貞は明治二十二年三月二十八日、八十五歳で没している。継之助が没してから二十二年近くも生きたことになる。
貞は勝気ながまん強い雪国の女性だった。生来、経才があったというが、その才能は子に引き継がれたのだろう。亡くなる半年前、郷土史家で新聞人の広井一が、貞に会っている。暗い一室に、凜として据っていたという。
その貞が一番つらい思いを語っている。それは戦時中、潜伏先の濁沢村阿弥陀寺で襲われて捕えられたことだった。住職の神田月泉の配慮も空しく、高田に護送されて半年間の禁固に会った。「唐丸籠に乗せられた思いは生涯忘れません」と語っている。妻のすがはその際、髪をおろしている。
その貞のところに、毎年、継之助の命日近づくと訪問する老人がいた。古志郡加津保村の元庄屋鈴木総之丞である。号を訥叟という。藩政時代、継之助に北組の割元を命ぜられ、郡政改革に一役を買った人物だ。当時、栖吉村の紛擾に困り果てた継之助は、あるとき仮病を使い、総之丞を病床に呼びよせた。そして息もたえだえに栖吉村の庄屋職就任を懇望する。総之丞はそれほどまで評価してくれると感激して、涙ながらに受け入れると「がばっと」継之助が起きて、喜んだというのである。その際、継之助は一番大切にしていた師の山田方谷の書を総之丞に渡している。継之助が戦争中、敗走の道を追求し、直接「北組割元職」の返上を申し出ている。律義な性格だった。
その総之丞に向って、母の貞が、
「世間様は、継之助がやったことを悪し様に申しまするが、本当にそうなのでしょうか」
と長岡弁でたずねたという。その際、総之丞は訥弁で、
「そうは申しても、いつかは継之助様の真意がわかるときがきましょう」
と答えたという。そして二人は遠く東の方を眺めて、無言の刻をすごしたとある。
(稲川明雄)

【稲川通信18】継之助の屋敷跡
ほんの最近まで、河井継之助の遺族が建てた屋敷が残っていた。戊辰戦争前の河井屋敷は戦火で焼失してしまったから、再築したものである。
長町一丁目の入り口に継之助の屋敷があった。今はないが、小路の右角に二本の松があった。玄関から入ると客間があり、その奥に六畳と八畳間があり、またその奥に三畳間があって台所があった。この家は戊辰戦争後、継之助の父、代右衛門を母貞、そして妻のすがが潜やかに住んだ家であった。
北側に縁があり、広い庭園があった。それは河井家の昔の面影をとどめる唯一の庭であった。これは、今もその面影を失っていない。井戸の跡、灯籠、石畳、ちいさな樹木は、継之助の慈しみが今も残っているようである。
建物は近代的な建築に変わってしまったが、長町の小路は昔のままであるし、その両側には侍屋敷がつらなっていたことを想像させてくれる。
この地で継之助は生まれ育ったのである。河井邸の向いには、小林又兵衛の屋敷があった。文政十一年生れの虎三郎は、よく遊んだことであろう。
僧良寛がたずねてきたのも、長町の屋敷であった。父代右衛門は風雅を愛し、刀剣の鑑定に秀れた才能を持っていた。
号を小雲と称し、茶事を好んで聴松庵・虚白庵と称した。虚白としたところが面白い。
(稲川明雄)

【稲川通信17】榎木峠と司馬遼太郎の碑
長岡から南へ、小千谷に向かう途中に妙見堰がある。妙見堰は信濃川が魚沼の山間から、流れ出る隘路あいろに平成五年にできた。その堰に沿うように越の大橋が架けられ、その西詰に司馬遼太郎が河井継之助を謳った石碑がある。碑は信濃川をはさんで、対岸に聳える榎木峠、朝日山の古戦場が眺められる。
石碑の表には司馬遼太郎の代表作「峠」の一説が記されている。問題は碑裏の文章だ。『峠』のことと題する司馬遼太郎の河井継之助を視た眼が紹介されている。
越後長岡藩に河井継之助があらわれた。かれは藩を、幕府とは離れた一個の文化的、経済的な独立組織と考え、ヨーロッパの公国のように仕立てかえようとした。継之助は独自の近代化の発想を実行者という点で、きわどいほどに先覚的だった。
ただこまったことは、時代の方が急変してしまったのである。にわかに薩長が新時代の旗手になり、西日本の諸藩の力を背景に、長岡藩に屈従をせまった。
かれらは、時の勢いに乗っていた。長岡藩に対し、ひたすらな屈服を強い、かつ軍資金の献上を命じた。継之助は小千谷本営に出むき、猶予を請うたが、容れられなかった。といって、屈従は倫理として出来ることではなかった。となればせっかく築いたあたらしい長岡藩の建設をみずからくだかざるをえない。かなわぬまでも、戦うという美的表現をとらざるを得なかったのである。
かれは商人や工人の感覚で藩の近代化を図ったが、最後は武士であることのみに終始した。武士の世の終焉にあたって、長岡藩ほどその最後をみごとに表現しきった集団はない。運命の負を甘受し、そのことによって歴史にむかって語りつづける道を選んだ。
『峠』という表題は、そのことを、小千谷の峠という地形によって象徴したつもりである。書き終えたとき、悲しみがなお昇華せず、虚空に小さな金属音になって鳴るのを聞いた。
平成五年十一月 司馬遼太郎
司馬遼太郎が腹部大動脈瘤破裂で亡くなったのは平成八年二月十二日。これより数年前小千谷市公民館館長の山本清さんが司馬先生に碑文を依頼すると心よく引きうけ、原稿を送ってきたという。但し書きに活字にして欲しいとあった。
(稲川明雄)

【稲川通信16】方谷の述懐
方谷の元にいたころの継之助は、三十三歳。たぶん、方谷門下で、もっとも知略に秀れた者のひとりであったろう。方谷はその継之助に期待したものがあった。
入門時、単刀直入に知性ではなく作用、つまり知謀を知りたいという継之助の人物に魅せられた方谷。その師弟は松山滞在中、あらゆる改革の手法について語り合ったと伝えられる。塵壺にはその模様は書かれていない。おそらく別冊にし、それは大切に保管していたが、何らかの事情で失ったかもしれない。
ただ、継之助には陽明学の神髄を知ろうという書生ではなく、その作用を知ろうとした気概、つまり志があった。その志を佳よしと方谷は改革の要諦を懇切に教えたという。
だから、方谷は継之助の生涯に不安を憶えその行く末を心配している。
臨終近い継之助が松屋吉兵衛という商人に「方谷先生の教えを最後まで守りましたと伝言してください」といったと聞き、方谷は一言も発しなかったという。また弟子の三島中州を通して、河井継之助の遺族を引き取りたいと申し出もしている。
八十歳近くなった方谷は、継之助の碑文を頼まれている。その際、方谷は「碑文いしぶみを書くもはずかし死に後れ」と固辞している。
多分傑作を創り出したと思っていた方谷が、継之助の死を知り、おのれの学問を重ね合わせたのだろう。
(稲川明雄)

【稲川通信15】容貌と性格
明治十八年六月に出版された『北越名士伝』に「河井継之助ノ伝」が所収されている。恐らく、河井継之助伝記としては嚆矢であろう。この著述は松井広告がしたものだと、後年告白しているが、大橋佐平の筆になるものと今まで解釈されてきた。たとえ佐平が執筆していなくても、佐平が校閲したことには違いない。
『北越名士伝』では河井継之助の容貌をつぎのように記している。
君、性豪活、夙に俊邁の気あり。身駆甚だ低からず。肥瘠、其の中を得、黧くろく、眉秀で、眼光烔々として、人を射る。一喝いっかつ、睥視すれば、即ち人、仰ぎ見る能はず。言語清朗にして、最も弁舌に長ず、叱咤しった、席を打て弁するときは、議論風生、凛として犯す可らざるの威ありと云ふ。
松井は河井継之助とは会ったことがないので、佐平から聞いたものにちがいない。町奉行の時河井継之助は、町政をを弾劾し、町役人を処罰した。そのときの印象を大橋佐平が記したのであろう。
それにしても、悠久山公園に建つ「故長岡藩総督河井君碑」の明治二十三年八月の三島毅の印象と見比べると面白い。
君、大顱だいろ方面、眉秀でて眼凸、爛々たることの雷いかずち如し。或いは怒りて、眥まなじりを決すれば、人よく仰ぎ見るなし。天資、英敏明快、一見して人の肺肝を洞つらぬく。姦偽を排し、尊貴を避けず。忠良を愛し、賤賎を遺さず。自ら信ずること尤も厚く、死生を顧みず、毀誉きよを問わず、事は必成を期して、措置縝密しんみつ、克きく艱楚かんそに耐え、言論爽快、能く是非弁析し、一座屈服す。
大橋佐平の視た河井継之助の容貌と三島毅の感想がほとんと一致している。今、伝わっている彼の肖像写真は、校正されたものだという。柔和な顔立ちの三十三歳が、実際は目の鋭い怖そうな顔立ちであったとみると面白い。
(稲川明雄)

【稲川通信14】河井継之助の墓
長岡市の東神田に光輝院栄凉寺という浄土宗の寺院がある。寺紋に藩主牧野氏の丸に三葉柏の御紋をいただく由緒正しい寺院である。歴代長岡藩士の墓所もあり、牧野氏の菩提所である。
その墓地の奥まったところに継之助の遺骨を収めた河井家の墓がある。墓石には「先祖累代之墓」と刻まれ、「秋恒建之」とある。秋恒は継之助の祖父である。河井継之助三代目の当主。その才覚は秀でており新潟町奉行などをしている。たぶん、秋恒が没するころの文政の頃に建てたものと思われるが、それはまた、河井継之助が生まれるころに相当する。
正面に向かって右側に温良院・忠良院・峰寿院の戒名が並ぶ。妻すが、河井継之助、母貞の順である。その他の二面に褁珠院(河井継之助初代代右衛門信堅)・宝真院(二代代右衛門秋高)・瑞麟院(三代代右衛門秋恒)・仙寿院(四代代右衛門秋紀)ほか計十一名の戒名が記されている。
河井継之助の遺骨が、会津若松の建福寺から栄凉寺に移葬されたのは、明治三年十月七日のことである。継之助の従者であった松蔵が会津を案内し、森源三らが携いて帰った。
松蔵の直話として、「我が旦那様の遺骨を棒持して、長岡に戻り、御母堂及び奥方様にこれを手交する。敏捷なりと賞してくださる」とある。
森源三は老公牧野忠恭の命によって河井継之助の遺族を扶養した藩士であった。あたかもその直後に長岡藩は廃藩した。
河井継之助の墓所は森源三の次男茂樹が河井家の養子となり、その子孫によって守られることとなった。
(稲川明雄)