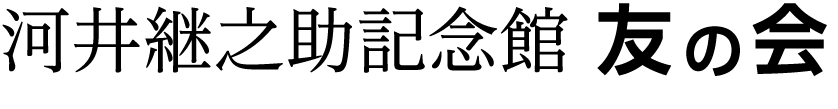【稲川通信35】江戸遊学
嘉永五年(一八五二)春。継之助は待望の江戸遊学に旅立つ。妻のすがには「なに、川をひとつ渡り、山をひとつ越えれば江戸さ」と言い、すたすたと旅立っていったという。
遊学の宿志は、もとより己れの立身である。己れの人生を、この遊学にかけていた気配が濃厚である。二十六歳の遅い旅立ちだったが、一緒に同行した若い友たちがいた。同藩士永井慶弥(のちの立花逸造)らである。この立花らが、のちに河井継之助の人間像や藩政改革の実際を証言することになる。
継之助らの遊学は、藩庁の許可を得たとはいえ、全くの私費での旅行、三国街道を上のぼるにも気概は横溢おういつ、気楽なものであったという。
街道の途中、景色の良いところのくると、立ち止まって放吟したり、旅宿で酒を飲んで酌婦とたわむれたりして、壮士が青雲の志を抱くような華やかさがあった。この反対に公費で遊学の途についた友の小林虎三郎などは、悲愴ひそうな覚悟で三国峠を越えたという。
継之助は生涯、三、四度、三国峠を越えている。三国峠は、越後・信濃・上野の国境にあることから名付けられた。越後から下れば、そこはまさに異郷。新天地となるか、魔境となるかの境目にあたっていた。二度目の遊学は冬期だったから、信濃路を通って碓氷峠を越えた。文久と慶応に継之助は三国峠を越え、帰郷しているが、そのたびに歴史の天命というものを背負って帰ってきている。
(稲川明雄)